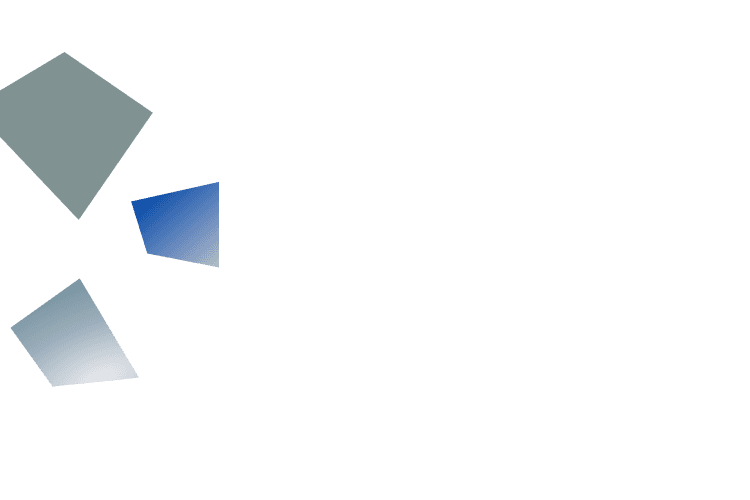
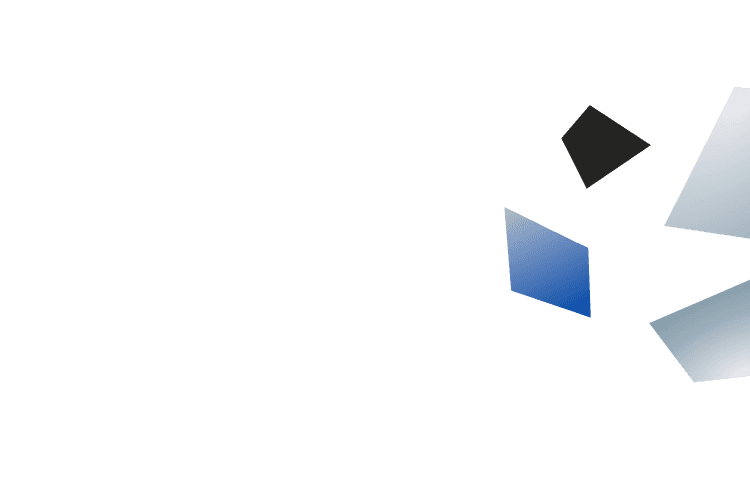
風とタルト
※この小説は実話を元にしたフィクションです。




どこまでも続く青空と緑。車の窓を開けると、木々の香りと夏の終わりの匂いが髪を揺らした。吉岡は転職して4か月。遅めの夏休みで長野に来ている。東京では味わえない空気をいっぱいに吸い込んでは、肩に入っていた力を息にのせて抜いていく。新しい環境での緊張と高揚を手放しつつある旅行中日のことだった。
車内の音楽が止まり、着信音が流れる。
さっきまで肺を満たしていた空気が喉でつかえる。画面に浮かぶ名前は勤め先の代表である相原だった。休暇中にくる電話。心地よかった木漏れ日が、暗い影に変わる。
「お疲れさまです」
できるだけ落ち着いたトーンで出ると、相原は興奮ぎみに
「やばい!あとでチャットみて!」
とだけ言い放ち電話を切った。車内に再び音楽が流れる。吉岡は混乱しつつも、彼の声色から悪い知らせではないことだけはわかった。スマホを覗くと相原からチャットが来ていた。吉岡は短く息を吐いてから開く。
相原「ヴァンベールのLP制作の話きた!!!」
いつか一緒に仕事をしたいと思っていたブランドの名前が目に飛び込んだ。吉岡は描いていたより3年早く現実味を帯びる夢を前に「もうきてしまったか」と一瞬おののく。だが次の瞬間には「いける」といつもの前向きで力強い彼女に戻った。心はドライブ用に組んだプレイリストよりも高鳴っていた。
相原はこの話が来た瞬間、右からは楽しみが左からはプレッシャーが、均等に心臓を打ちつけるのを感じた。そのビートは早く、会社にとって重要な挑戦であることを告げている。
ヴァンベール(Vent vert)はフランス語で緑の風を意味する。相原も動向を追いながらリスペクトしていた新進気鋭のフルーツタルトブランドだ。タルトに使うフルーツは代表自らとパティシエが東京から産地まで足を運び、生産者と直接話して仕入れを決めている。品質はもちろん、想いが一致しお互いがプラスになることを丁寧にすり合わせたものしか使っていない。商品は素材の特色を最大限に活かすべく、精密に作り込まれ、華美な装飾はない。偽りなく研ぎ澄まされた哲学、世界観、味に多くのファンがついていた。実店舗は都内に一つのみで、ここでのコミュニケーションを大切にしている。最近はオンラインでの販売にも乗り出し、D2Cのスイーツブランドが乱立する中で異質な存在感を放っていた。そのブランディングは秀逸でマーケティングの世界でも名前があがる。中でも昨年取締役に就任した小野寺は他業界で思想と売上の両立に貢献しており、相原と吉岡も移籍前から尊敬している人物だった。それゆえにヴァンベールの仕事をすれば、広い業界から注視される。
さらにこの件の紹介者は、以前一緒に仕事をした広告代理店の関根だった。とにかく頭が切れ、情報収集の感度が高い。ヴァンベールのオンラインショップやSNSまわりを初期から担当し続けている敏腕プロデューサーだ。そんな関根の声かけというのは、嬉しさと同時に引き締まる思いだった。
関根から告げられたヴァンベールのリクエストは、築き上げたブランドを守りながら新たなファンと出会い、購買まで繋げるLPの制作だった。コロナ禍になりオンラインでの売上をより強化したい意向があるという。関根は相原以外にも声をかけており、他社に決まる可能性も残っている。
相原はこの相談がきた瞬間、吉岡をアサインすると決めていた。彼女が以前からヴァンベールのファンであり小野寺を尊敬していることを、相原はSNSを通して知っていた。そして何より、吉岡を採用したのは世界観への深い没入度と圧倒的なセンスをもっていたからだ。このプロジェクトを担うには彼女しかいなかった。というより、プロジェクトのほうが彼女の入社を待っていたかのようだった。
相原が会社を立ち上げて10年ほどが経ち、業界の流れは転換点を迎えていた。LPといえば「いかに購買意欲を掻き立てるか」だったが「世界観やブランドを大切にするもの」を求められる空気が漂いはじめたのだ。社内のメンバーたちは精鋭ではあるものの、前者のLPを極めてきている。今後より世界観を重視したプロジェクトがくることを予想し、相原は後者のLPを任せられる人材の採用を決めた。
そこでオファーをして入社が決まったのが、吉岡だったのだ。まるで空から見られていたかのようなタイミングで、チャンスの糸が頭上でふわりと揺れている。




吉岡が休暇から戻ると、二人はすぐに都内に唯一あるヴァンベールの店舗へ向かった。彼らはできる限り足を使い五感すべてをブランドに捧ぐ。
最寄駅から店舗へ向かう道。広い通りに秋色に染まるのを待つ木々が並び、葉の隙間から覗くベランダでは穏やかな生活が風に踊っている。その1階には店主のこだわりが小さな扉から品よく漂う、美容院やカフェ、ドライカレーの店などが入っている。大通りから一本奥へ入ると、どっしりと佇む家が並んでいた。こういう場所に店を構えるブランドなんだ、と相原は肌で感じとる。店に着く前からブランドの想いは息づいているのだ。どんな想いでこの地を選んだのか、お客さんはどんな気持ちでこの道を歩いてくるのか。吉岡の没入度のレバーもすでに深いところまで引かれていた。
到着すると、写真で見るよりあたたかな光が店内を照らしていた。ブランドロゴが掲げられただけの白い壁は、遠目にはスタイリッシュに映るが近づくと手触りの残る漆喰で塗られている。特別感と親近感のバランスが絶妙で、二人は躊躇なく扉を開けた。ほのかに甘い香りが浮遊する中で、店員がマスク越しでもわかる朗らかな笑顔で客と会話している。
「りんごタルトは紅玉というりんごを使っておりまして、酸味と香りがしっかりとした品種なんです。仕入れ先の青森の農園さんが、収穫までできるだけ葉っぱを残すことで光合成をたくさんさせて、自然の旨味がしっかり出るように栽培されておりまして。色むらができやすいのであまりスーパーには出回らないのですが、当店では味重視で仕入れてタルトにしています。すごく香り豊かなのですが、香料は使っておらずりんごそのものの香りなんですよ。爽やかなお味で、私も1ピースをペロッと食べちゃいます。よろしければご試食いかがですか?」
りんごタルト一つで、これだけの知識とこだわりを語れる接客。自信と誠実さが現れる試食の提供。客がタルトを一欠片口に入れると、さらに会話が重なっていった。覚えたことをそのまま言っているのではなく、想いを込めて語っているのが伝わってくる。そして客は味だけでなくストーリーと出会い、地方の農園を知る。相原と吉岡はリアル店舗でも徹底されて息づくブランドの世界観を感じた。
相原は初めてヴァンベールのタルトを口に運ぶと、一点を見つめたまま味覚と嗅覚、舌の感覚が冴えわたるのを感じた。今まで食べたことのないタルト、いや、したことのない体験だった。口に入れた瞬間、やわらかくも食感の残るりんごが爽やかに香り、軽やかなカスタードの甘味がりんごの酸味と溶け合ってふわりと口の中に満ちる。そこにさりげなく紅茶が香るタルトの生地がサクサクと交わり、喉をやさしく通り過ぎていった。最後に再びりんごの香りが脳の奥で色濃く余韻を残している。不思議と太陽に照らされる農園の情景が浮かんだ。りんご本来の香りや味を主役に他の素材の主張を最低限に調整された、上品で奥深い味わいだ。
瞬きを忘れる相原を見て、吉岡は少し誇らしげに笑いながら「いや、そうなりますよね、わかります。私も初めて食べたとき衝撃的でした」とタルトを口に運ぶ。「あ〜おいしい」と今日一番の笑みがこぼれた。
季節のタルトを一通り試食したあと、定番のいちごタルトを勧められた。その後に併設のカフェで頼んだものも含めると、気づけば二人で三人分のタルトを食べていた。それほど自然な美味しさでふわりと胃に落ちていく。帰宅してから胃もたれしていないことに驚き、「あんなに食べたのに!!」とチャットで笑いあった。
ヴァンベールのサイトは世界観も作りこまれており、商品紹介はもちろん、製造過程や想いまでが丁寧に綴られている。インターネットを通してもその洗練された世界観や哲学は届いてくるが、やはり体験に勝るものはない。ブランドの外側にいた人間が、ここまでブランドを作りあげてきた人たちの想いを正確に汲み取るのは、想像以上に難易度が高いのだ。できる限りのことを準備したうえで、慎重にヒアリングをしてやっと目線が重なっていく。




迎えたヴァンベールチームとの最初の打ち合わせ。オンラインで課題のヒアリングとディスカッションを行う。先方は取締役の小野寺、Web担当の湯浅、紹介元の広告代理店から関根が同席する。
側からは和やかにも受け取れる雰囲気だ。しかし、相原と吉岡には透明の糸がピンと張られている。ヒアリングがはじまると糸によりテンションがかかった。小野寺と湯浅がこれまでにない解像度の高さで課題を語りはじめたのだ。他の多くのプロジェクトでは課題認識の時点で、相原と吉岡がマーケティングのプロとしてブランド側が見えていない部分を照らし直すところからはじまる。しかしその必要がほとんどなく、最初から同じルーペを一緒に覗いていた。さらにヴァンベールの二人が使う言葉一つ一つの裏側にブランドの哲学が横たわっているのを感じる。外の者が少し違う表現を使ってヒビが入れば、そのまま一気に深い溝となる緊張感があった。相原と吉岡のこれまでの経験と知識、そして入念な事前準備によるブランド理解がそのまま相手に伝わっていく。
だが相原はその状況を楽しんでもいた。同じものを見つめながら会話が進んでいくこと、ブランドを築きあげた小野寺たちの思考を直に聞くこと。相原はこれまでにないほどアドレナリンが出ているのを感じた。吉岡はそのすべてを自分の中に吸い込ませようとしていた。
ここでのディスカッションと過去のプロジェクトの裏側を公開した記事が小野寺たちに刺さり、正式にこの案件を相原たちが担うことが決まった。
今回作成するのはこの秋から冬に推していきたいゆずタルトのLPだ。使っているゆずは、高知県北川村産。植えてから実がなるまで18年と言われるゆずは種から育った実生のものが希少で、接ぎ木を使って4〜5年で収穫されたものが多く出回っている。しかし北川村は古くからゆずの産地であるため、実生のゆずが多く生産されているのだ。手間はかかるが、香りと酸味が強く味も深い。国内の老舗料亭や高級レストランでも使われており、タルト発祥の地フランスでも評価を得ている。そんな高品質なゆずだが、産地では農家の高齢化や人手不足といった課題も抱えている。ヴァンベールチームからはこうした産地のストーリーを伝えつつ、品質や味も伝えたい。既存のお客さまが見ても新規のお客さまが見ても惹かれるサイトにしたい。というお題があった。
異なる客層に響く見せ方と情報、情緒的でありながら購買にも繋げたい。相反する要素が同居する難易度がありながらも、バランスを熟考しながらLPの方向性や構成、デザインは比較的スムーズに決まっていった。写真はシンプルなタルトながらしずる感が出るよう吉岡が指示書を書き、ヴァンベールチームが撮影。息のあった連携でイメージ通りの仕上がりだ。スケジュール通りでどんどん完成へと進んでいく。
しかし一つ、最初に決まる予定のものが最後まで残っていた。キャッチコピーだ。社内のメンバーがオフィスに集まりゆずタルトの試食をした際も「おいしい!」「うまっ!」の次に出てくるのは「これ、どう表現する?」だった。相原も、コピーを書く吉岡も、その言語化に頭を悩ませていた。
コピーは書いている時間よりも下準備の時間のほうがずっと長い。吉岡は競合のサイトをいくつも見て、雑誌や専門誌を読み漁り、言葉を集める。店舗での体験を鮮やかに呼び起こす。それからゆずタルトを家に送り、夕食後に食べては夜な夜なコピーを書き続けた。実際に購入した人たちが食べるのと同じ時間に、同じ気持ちで書く。すべての感覚を使ってコピーを書く。彼女は一度集中すると声をかけても聞こえないほど没入する力をもっていた。しかもそれが持続する。そうして、100本のコピーを書きあげた。いくつかに☆をつけてすべてを相原に提出する。
相原は、やはり吉岡にこのプロジェクトを任せてよかったと思った。入社してからまだ数本目の案件だが、前提のズレがなかったのだ。日の浅いメンバーと提出物を前に前提から確認し直すという経験は多くある。だが、彼女には必要なかった。相原は100本すべてのコピーに目を通す。方向性はぴったりだ。
だがこれだと決めきれるものはなかった。吉岡ならもう一段、まだ踏み込めると信じていた。相原は☆がついていない候補からもいくつかピックアップし、「いい!この辺でもうちょい出してみて、まだいける」と返す。
吉岡は心の奥で灰色の気体が渦巻くのを感じた。一切妥協はしていない。それゆえに「もう出ないよ」という憤りが相原に向かう。相原は吉岡の表情が曇るのを感じて心苦しく思いながらも「あとちょっとのところまではきてる!」と明るく重ねた。吉岡は再びコピーに向き合うと、熱を帯びた眼差しに戻っていた。
こうして相原と吉岡の間でブラッシュアップを重ね、コピーはLPの他のすべてが完成している段階で候補が固まった。最後に吉岡が6案まで絞り、先方に提出する。
小野寺「これでいきましょう!」
返事がきて、二人は「よかったぁ〜」と語尾にたっぷり空気を乗せた。そこからはチームのメンバーと連携しながらページを完成させる。最終確認が終わると、相原は会食のため早い時間にオフィスを後にした。吉岡もやりきった表情で先方に公開前の確認用ページを送る。明日には返信がくるだろうと、長い息を吐き、伸びをした。その背中を秋の燃えるような夕陽が照らしていた。




少しだけ開いた窓から、冷たい夜風が心地よくデスクに届く。2時間ほどが過ぎた頃、吉岡はいつもの集中用プレイリストではなくお気に入りの曲を聴きながら、別の仕事に取り掛かっていた。
スマホは、少し冷めたカフェラテの向こうで伏せられている。取引先との連絡が落ち着くこの時間帯は、吉岡にとって作業のゴールデンタイムなのだ。2か月ほど肩にのっていた重みから少し解放された手が、キーボードを軽快に叩いているところだった。
イヤホンの音楽が止まり、着信音が流れる。
デスクの上で震えるスマホを慌てて取り上げると、抜けていた力が全身に戻った。着信は会食中のはずの相原からだった。心臓の内側が大きく上下する。
「はい」
できるだけ落ち着いたトーンで出ると、相原は興奮ぎみに
「チャットみて!」
とだけ言い放ち電話を切った。「え、何?」吉岡は心の中で呟きながら、少し力が抜ける。戸惑いながらも、彼の声色からトラブルではなさそうだとわかった。音楽を一時停止してスマホを確認する。ヴァンベールチームとのグループチャットに小野寺からのメッセージが届いていた。吉岡は短く息を吐いてから開く。
小野寺「テストアップ確認しました。いや、もう最高です。最後の最後までご尽力いただき本当にありがとうございました!」
小野寺「2月の旬に向けていちごタルトのLP制作もぜひみなさんにお願いしたく、ご相談させてください!」
相原「ありがとうございます!うれしいです!ぜひお願いします!!!」
相原「会食中で取り急ぎのご連絡ですみません!」
仕事の依頼ほど嬉しい褒め言葉はない。吉岡は残っていたカフェラテを流し込むと、もう一度チャットを読み返した。いつか一緒に仕事をしたいと思っていたブランドが、また一緒に仕事をしたいと言ってくれる。これ以上ない夢の叶い方だった。あの日、頭上で揺れたチャンスの糸。その先端をかかとを上げてぎゅっと掴むと、握った手を緩めることなく描いていたより遠くまで走り続けてきたのだ。
相原はスマホを置いても、頭の半分は会食から遠ざかっていた。浮かべていた笑みの半分は依頼の嬉しさからだった。
ゆずタルトのLPが公開されると、息つく間もなくいちごタルトのプロジェクトが始動した。いちごタルトは相原と吉岡も店舗で食べて絶賛していた定番人気商品だ。そんないちごタルトを、今回はいちごの旬でありスイーツ界がストロベリーフェアで盛り上がる時期に、まだヴァンベールを知らない人にも購入してもらうLPを目指す。季節性と独自性があったゆずタルトと比べると、定番人気商品を改めて紹介するのは難易度が高い。さらに競合が増える商材、シーズンと壁が重なる。
ヴァンベールチームからオリエンがあった後、相原と吉岡はリサーチを進めながら頭を悩ませていた。いちごを説明する言葉は、甘さと酸味のバランスでどうしても似通ってしまう。見た目を華やかにすることで惹きつけるブランドが増える中、ヴァンベールのタルトはシンプルだ。一番の特徴である『香り』は表現が難しい。製法にこだわっているもののエントリー層にいきなり打ち出すには距離があり、伝え方に工夫が必要だ。二人の頭には、それぞれ自宅で大きなキャリーケースに荷物を詰めている間もぐるぐるといちごタルトのことが駆け巡っていた。これから二人は他のメンバーたちと共に、別の仕事の都合でロサンゼルスへ向かうのだ。そのまま年末年始を過ごすため、滞在は1か月ほどになる。プロジェクトの半分は向こうで進行していく予定だ。
羽田からロサンゼルスまでのフライトは10時間。相原と吉岡は太平洋を横断する夜空の上で、いちごタルトについて話していた。商品の難易度が高いうえに、ゆずタルトで上がったハードルを超えていかなければならない。




身体が時差に慣れた頃にやってきたヴァンベールチームとのディスカッションの日。相原と吉岡はビーチにいた。オレンジとピンクとブルーが溶け合う空で、太陽が水平線に向かっている。背の高いヤシの木の葉がゆるやかな海風に揺られている。すぐ側にはスケートパークがあり、子どもから大人までが次々と技を決めていた。二人は少し静かな砂浜まで歩くと、スマホからミーティングに参加する。
ロサンゼルスの話で場があたたまった後、議論が始まると熱は一気に高くなり空気が変わる。相原は高い視座でスピード感をもって繰り広げられる小野寺と湯浅とのミーティングがたまらなく好きだった。卓球のダブルスのように四人は緻密なラリーをテンポよく重ねる。気づくと1時間、夢中で話し続けてスマホを閉じた。夕陽に照らされていた波の姿は暗闇に隠され、音だけが響いている。
まだ高揚感が残る身体から長い息を吐く。吸い込んだ空気が少しひんやり感じ、心臓がきゅっと縮んだ。きっとさっきのスケートボーダーたちも、あの高い場所から滑り出す前はこんな感覚だったのだろう。頭の中でわくわく描いたものを実際に出せるか、というプレッシャーが押し寄せてくる。打ち合わせが終わった後は、いつも違う汗をかいていた。
いちごタルトのLPの方向性は、ゆずタルトよりもシックなデザインでいくことになった。ブランド立ち上げ時から王道商品であり続けるいちごタルトの位置づけを表現しながら、他社のいちごスイーツの華やかな見せ方と差別化を図る。タルトの特徴や製法のこだわりは、動画やアニメーションを使いながらわかりやすく紹介し親近感を出していく。さらにゆずタルトでも提案した飲み物とのペアリングを、レパートリーを増やして掲載する。既存のファンにも新たな楽しみ方を提案する狙いだ。写真は商品ページのものがあったが、追加で撮影を入れることになった。
撮影やペアリング提案は今回も吉岡がリクエストを出しながら、ヴァンベールチームが素材を担当する。プロジェクトに関わる誰もが、いいものをつくるためには手間を惜しまないメンバーだった。東京とロサンゼルス。17時間の時差がありながらも、2本目ならではのチームワークで日本に残る社内メンバー、そしてヴァンベールのメンバーと連携しながら、年内予定のスケジュールは順調に進んでいった。




無事に年末年始を過ごせそうだとほっとしていたのも束の間、相原と吉岡を含む数人が陽性となってしまった。滞在していたコンドミニアムに籠り療養する日々が1週間ほど続く。
ようやく外に出られるようになった日。ロサンゼルスの食事に飽きていた一同は、回転寿司に向かった。久しぶりの外食、久しぶりの日本食。吉岡は寿司を目の前にして、隣のテーブルでレーンの皿に初めて手を伸ばす子どもと同じ顔をしていた。一番好きな赤貝から口に運ぶ。
「……味がしない」
相原は「するよ?もしかして嗅覚……?」と返す。吉岡は後遺症で嗅覚を失っていることに気づいた。鼻をつまんで食べると味がしないと話には聞くが、いざ匂いがしなくなると本当に味の違いがわからなくなっていた。
その数日後。帰国の準備に取り掛かっていると、今度はフライトに必要な陰性証明書がなかなか出ない。仕事始めに出社する予定が大幅にずれ込んでしまう。相原は申し訳なさと気まずさで肩を丸めながら、東京のメンバーに帰れなくなったことを連絡した。
ようやく帰国できたのは、オフィスにいるはずだった年明け数日後だった。だが家に戻ることはできない。そのままバスで隔離施設まで運ばれていくのだ。同じ窓がひたすら均等に並ぶ寮の一室で、外へ一歩も出られない7日間がはじまる。吉岡は息が詰まりそうな部屋さえも集中する場所に変え、黙々と仕事を続けていた。いちごタルトのLPはシーズンに合わせた2月の公開を遅らせることはできない。
部屋のドア前に置かれたほとんど味のしない弁当を食べ終えると、スマホでメモ用のチャットを開いてさかのぼった。吉岡はフレーズが浮かぶと、その場で自分宛に送る。いくつも並ぶいちごタルトの表現。世界観は映せているが、もっといいレンズがある気がしていた。ぼんやりと眺めていると、回転寿司のできごとを思い出す。嗅覚を失って食べる寿司がどのネタもただ塩気を感じるだけだったように、匂いのしないスイーツはどれも甘いとしか言いようがない。味に個性を宿しているのは香りなのだ。
それに気づいた吉岡は、記憶を手繰り寄せて香りの表現を調整していく。すると、ややぼやけていたピントが絞られていく感覚があった。これだ、と吉岡は提出の形に落とし込んで送る。相原は「これでいこう」と返した。
小野寺「これでいきましょう!」
いちごタルトのコピーはこうしてスムーズに決まった。
そこから急ピッチでデザインやアニメーション作業が進められていく。アニメーションは適切な位置、タイミング、速度、大きさと要素が多い。ヴァンベールの飾らない自然な世界観を表しながら、スマホの小さな画面をぼんやり見ていても引きつけられる動きは難易度が高かった。ギリギリまでこだわり抜いて調整を重ね、ここまでロサンゼルスから帰国時のアクシデントがあっても遅れなかったスケジュールから一日遅れでFIX。そこから2社で培った見事なチームワークで巻き返し、予定通りに公開することができた。
2月としては異例の3月並みの気温だったこの日。少し開けた窓から春の夜風が、二人を労うように撫でている。そこに、小野寺からスマホの画面1スクロール分の感謝のメッセージが届き、相原と吉岡は身体が内側から熱くなるのを感じた。
その年の年末。吉岡は慌ただしい年内最後の撮影現場から、冷たくも不思議とあたたかみを感じる風のなかを歩いていた。
イヤホンから流れていたクリスマスソングが止まる。
忘年会に行っているはずの相原からの着信だった。この時期のトラブルほど背筋の凍るものはない。
「はい」
できるだけ落ち着いたトーンで出ると、相原は興奮ぎみに
「チャットみて!小野寺さん!」
とだけ言い放ち電話を切った。
※この小説は実話を元にしたフィクションです。
Writer:はつこ
お問い合わせはこちら
ランディングページ制作やデジタルマーケティングでお困りの方はこちらからお問い合わせください。
まずは打ち手をご提案させて頂きます。
ご入力いただきましたメールアドレス宛てに自動配信メールが届いておりますのでご確認下さいませ。
2~3営業日内に、担当よりメールにてご連絡を差し上げます。しばらくお待ちくださいますよう宜しくお願い致します。







